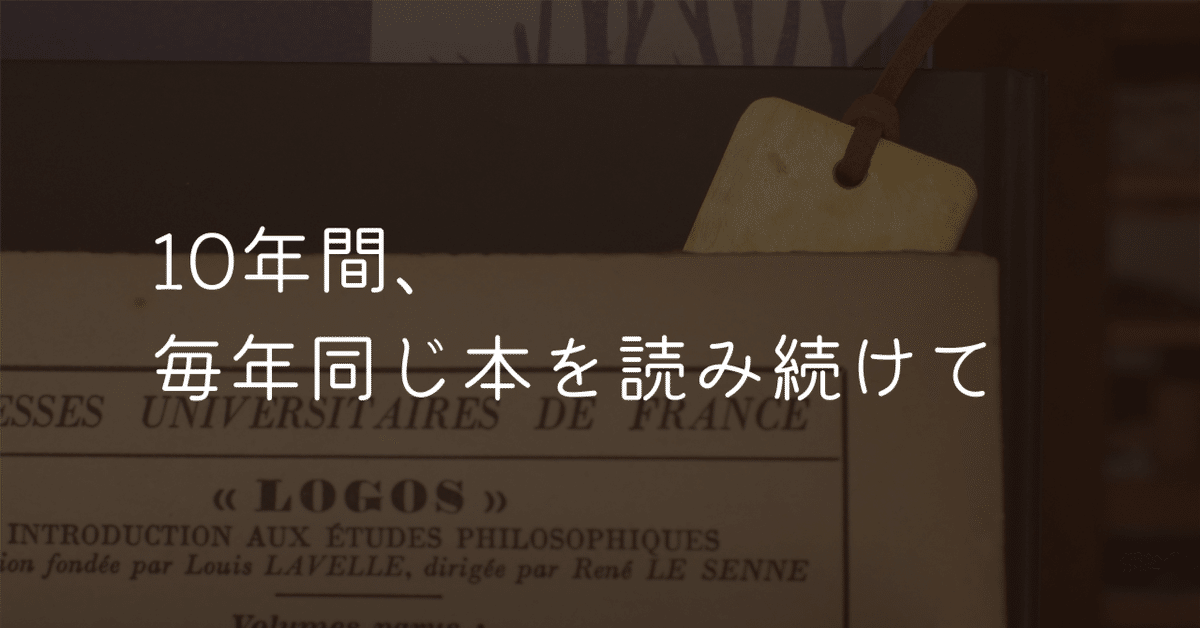2025/10/27 15:28
毎年9月に読み返す一冊の小説
先日から久しぶりに『九月の四分の一』という小説を読んでいます。作者は大崎善生さんで、初めて読んだのは大学生の時でした。
このタイトルがとても好きで、私の誕生日が9月ということもあって、当時は勝手にシンパシーを覚えていました。それがきっかけで、毎年9月にこの小説を読むようになりました。
『九月の四分の一』は短編集で、4つの作品が収録されています。表題作は最後の一編なんですが、約10年間ほど毎年読み続けていた中で、面白い発見がありました。
変わらない本、変わっていく自分
毎回読むたびに、好きな作品が変わっていきます。去年はこの作品が好きだったのに、今年は全く別の作品に惹かれる。何度も読んでいるはずなのに、まるで初めて読むかのような一文に出会うこともあります。
本の内容は変わらないのに、その時々の自分の状態によって響くものが変わっていく。この体験がとても興味深く感じられました。
妊娠、出産、育児という時期には、そんな余裕もなくなってしまい、同じ本を読み返すことも忘れていました。今年になってまた読書に触れる機会が増えて、久しぶりにまた読み返してみています。
読書は自分の「定点観測」
本の中の文章は、いつでも変わらずにそこにあります。
そんな「変わらないもの」に対して、自分が「変わっていること」を実感できる。去年と今年の違いを本を通して感じることができるんです。
読書は、物語や文章を楽しむこと以上に、自分の定点観測のような意味があると感じます。同じ本を定期的に読み返すことで、自分の内面の変化に気づくことができるんです。
子どもの成長を記録するアート
この考え方は本に限ったことではないなと思うことがありました。
先日、お客さんから伺ったうれしいエピソード。
その方は毎年お子さんの誕生日にキッズアートをして、私たちのアートタグを添えてくださっているそうです。アートタグは、子どもの作品にタイトルや日付を添えるもので、よりアート作品らしく飾ることができるアイテムです。
1歳のファーストアートから2歳、3歳と続けていて、毎年1枚ずつ作品が増えていく。それを並べて飾ると、筆のタッチや色の選び方の変化がよく分かるそうです。
同じことを続ける価値
毎年同じ本を読むことと、毎年誕生日に絵を描くこと。
ジャンルは違いますが、構造は同じだと感じました。
同じことを繰り返すことで、それ自体の意味(本を読む、絵を描く)だけでなく、変化が浮かび上がってくる。それがとてもおもしろいと思います。
本の場合は自分の内面の変化に気づくことができ、子どものアートの場合は成長という外に現れる変化がよく分かります。続けるということには、「続ける以上」の深い意味があると感じます。
続けることで見えてくるもの
これは私にとっての読書のおもしろさの一つでもあり、何かを続ける価値の一つだと感じています。変わらないものと向き合い続けることで、自分や大切な人の変化を実感できる。そんな体験を大切にしていきたいと思います。
家族との時間も同じかもしれません。毎日の何気ない瞬間を積み重ねることで、かけがえのない変化や成長を感じることができるのではないでしょうか。