2025/10/06 16:39
「褒めて伸ばす」という言葉、よく聞きますよね。 わが家の小1の息子はサッカーを習っています。 それが何でかなと考えたときに、「できたこと」は感覚が伴っているからかなと思いました。理屈では「今のプレーがいいプレーだった」ということがわからなかったとしても、「そうか、今のをもう一回やればいいんだ」ということが感覚的にわかる。 この気づきって自分にも当てはまるなと思いました。 大人も子どもも同じで、言葉より先に体験が必要なのかなと感じます。褒めるというのは別に甘やかすということではなくて、できた感覚を再現するためのフィードバックみたいなものなのかも。大人にとっても子どもにとっても体験が先で、言葉は後からついてくるものなのかもしれない。 だから私自身も「褒めて伸ばす」ということを少しずつ、体験として積み上げていきたいなと思います。完璧を目指す必要はないんですよね。まずは小さなことから始めて、実際に褒めてみる。その体験を積み重ねることで、だんだん感覚が身についてくるんじゃないかなと思います。理屈で分かっていても、やっぱり体験しないと本当の意味では身につかない。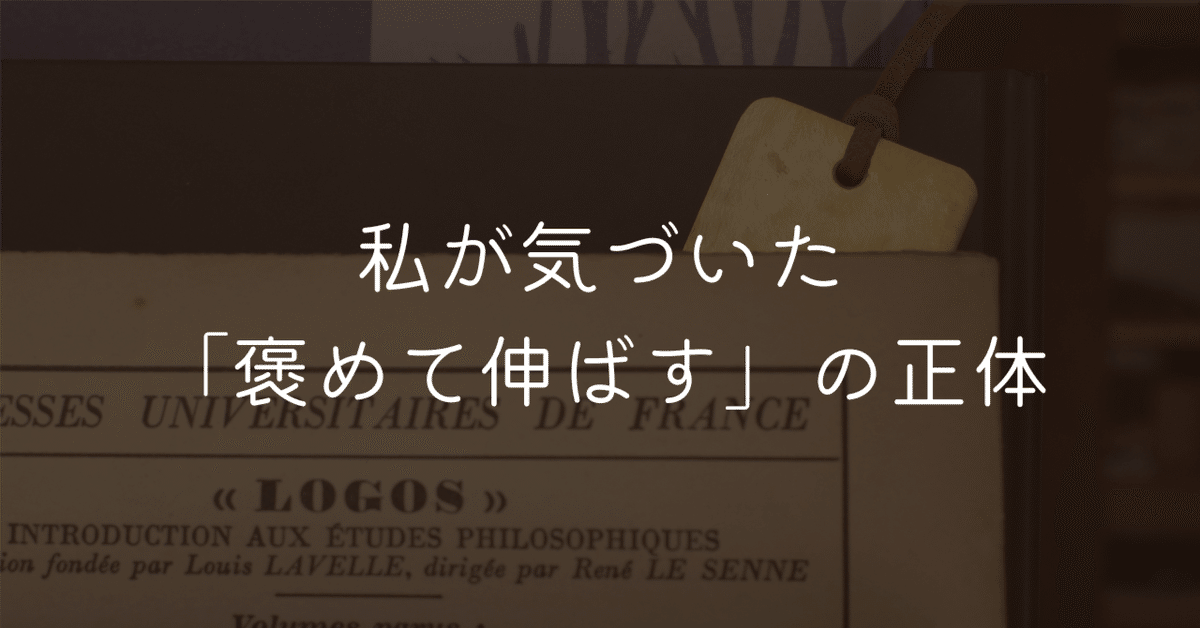
「褒めて伸ばす」って実際どうなの?
みなさんはこれについて、どんなイメージを持っているでしょうか?
「叱るより褒めた方が子どものメンタルにいい」とか「自己肯定感がアップする」みたいなことを思い浮かべる方が多いかもしれません。
私もまさにそうで、さらにこの「褒めて伸ばす」に憧れのようなものも感じていました。「そうできたらいいけど、実際はなかなかできない」という、もどかしい気持ち。褒めた方がいいことは、理屈では分かってるけど実感が全然伴わない。そして、結局いつものように「ここがダメ」「もっとこうした方がいい」と指摘ばかりしてしまう。息子のサッカーを見ていて気づいたこと
そのサッカーを見ていて、最近気づいたことがありました。
練習でも試合でも同じなんですが、できなかったことに対して「ここができてなかったよ」とか「パス出すならもっと前に出した方がいいよ」とか、できていないことを指摘をしても、子どもの体ってなかなか動かないんですよね。でも「今のそのパスの出し方すごく良かったよ」と言われると、それは再現できるんです。なんで褒めると再現できるのか?
実際に息子も「今のすごい良かったよ」と褒めたときに、「え、そうなの?」みたいな反応をすることがあります。
なぜそのプレーが良かったのかということを、頭では理解できなかったとしても、同じことをもう一度やることはできるんですね。
反対にできなかったことということを、「こういうときはこうしないといけない」と丁寧に説明すれば、しっかり考えて本人もきっと理解はできると思います。でもその言葉を理解するということに脳を使うと、それと体がリンクしない。体がついてこなくなっちゃうなと感じます。
子どもは特に、頭で理解するよりも体で理解するというか、感覚でつかむみたいなものが先にくるのかなというふうに感じます。「あ、これって私と同じ!」
この「褒めて伸ばす」という育児に、憧れはあるんだけど実感がないからできない。なんかつい指摘するようなことを言ってしまう。
理屈ではわかってるんだけど、体験が少ないから感覚がついてこない。
これって子どもができないことの指摘にピンときてないというのと同じ構造かなと思います。体験が先、言葉は後から
まずは体験から始めてみよう
