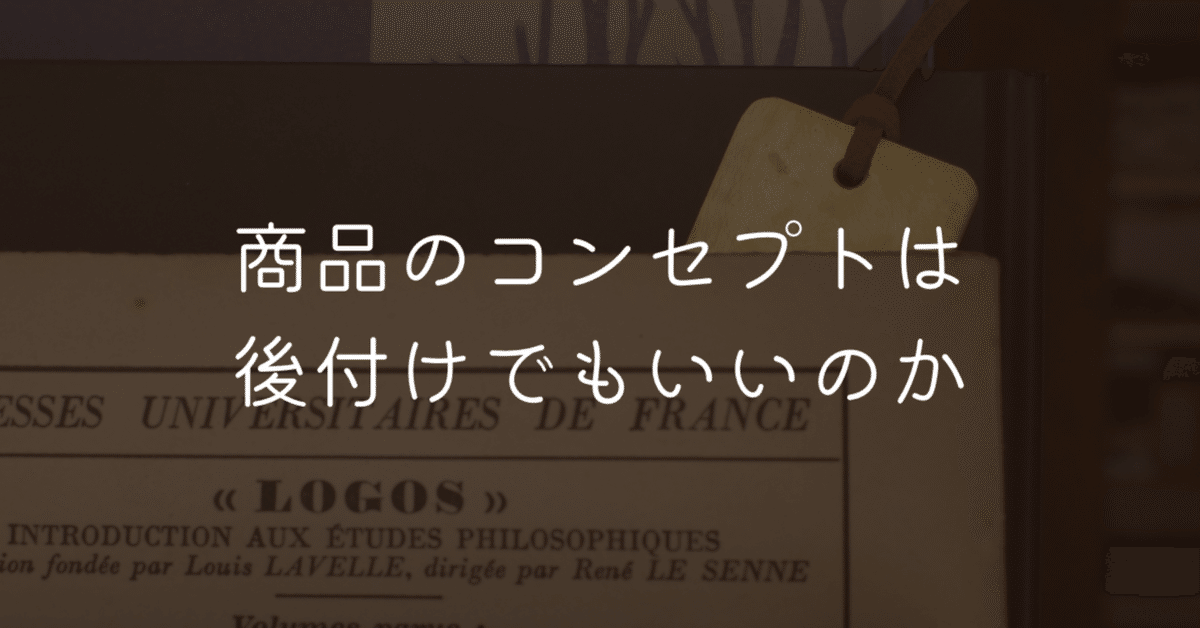2025/09/29 11:26
新しい商品をつくるにあたり、
コンセプトは後付けになってもいいのか?
夫婦で意見が分かれた出来事がありました。
私たちhattoは夫婦2人で運営していて、
デザインは夫が担当しています。
まず夫の普段の仕事について簡単に紹介します。
屋台カフェから生まれた偶然の産物
夫は本業で建築設計を手がけていて
学生と一緒にまちづくりの活動もしています。
その活動の一環として、
不定期で屋台カフェを開いています。
自作の屋台でコーヒーや紅茶を振る舞うという、
とても素敵な取り組み。
そこでコーヒーのドリップペーパーの
スタンドが必要になりました。
夫が「こういうのはどう?」と
簡単にスケッチを描いたところ、
参加していた学生さんがその絵をもとに
試作品を作ってきてくれました。
その試作品が予想以上に
可愛らしく仕上がっていたんです。
hattoのコンセプトとの向き合い方
そんな経緯があって、夫から
「このドリップペーパースタンドを
hattoの商品として扱うのはどうだろう?」
という相談を受けました。
hattoのブランドコンセプトは
「家族の絆をより濃く、より強く」
商品を通して家族のつながりを作ることを目指していて、このコンセプトをとても大切に考えています。
でも今回の試作品について考えてみると、
「このスタンドのコンセプトは何だろう?」
「このペーパースタンドで家族のつながりをどう作るのか?」
といった疑問が次々と浮かんできました。
どうにかしてブランドコンセプトに紐付けようと
試行錯誤してみたのですが、
どうしてもしっくりくるストーリーが
見つからなかったんです。
結局、商品化は見送ることになりました。
「後付け感」への違和感と夫の視点
この出来事を通して、
私は「物ありき」の発想について考えさせられました。
「こういうものがあるから売りたい」
「だからコンセプトをどう紐付けよう」
という後付けのアプローチは良くないのではないか。
そんな風に感じたんです。
でも夫は少し違う考えを持っていました。
「ピンとくるものがあれば、形から始まっても良いのではないか」と言うのです。
夫曰く、それは後付けということではなく、
「これ、なんかいいな」という「感覚」を
まだ言語化できていないだけなのではないか。
だから後付けというよりも、
その「感覚」に従って後から丁寧に言語化して、
ブランドに落とし込んでいけば良いのではないか、
という考え方でした。
感覚と論理、両方のプロセスを認める
夫の話を聞いて、私は
確かにその通りだなと思いました。
私たちhattoはいつも「家族の絆って何だろう?」
という問いから始まるものづくりをしています。
確かにそれも大切なプロセスのひとつです。
でもそうしたロジカルな方法だけでなく、
自分の感覚や直感に従って
「これいいな」と思うものから始まり、
そこからロジカルに落とし込んでいく
そんなプロセスがあっても良いなと感じました。
実際、優れた商品やサービスの中には、
最初は漠然とした「何かいい感じ」という直感から
始まったものも多いのかもしれません。
その直感的な魅力を後から分析し、言語化し、
ブランドのストーリーとして組み立てていく。
そんなアプローチも、
決して「後付け」として否定されるべきものでは
ないのかもしれません。
夫婦で運営することの価値
こうした議論ができるのも、
2人でブランドを運営しているからこその
気づきだなと改めて感じました。
一人で考えていたら、
私は「後付けは良くない」という考えに
固執していたかもしれません。
また夫も、「感覚重視で良い」という方向に
偏ってしまっていたのかもしれません。
でも2人で話し合うことで、
どちらか一方の視点だけでは見えなかった角度から
物事を捉えることができました。
感覚と論理、直感とコンセプト、
どちらも大切な要素であり、
状況に応じて使い分けたり、
組み合わせたりすることで、
より良いものづくりができるのだと思います。
ものづくりにおける「正解」はひとつじゃない
結局のところ、
商品開発に絶対的な正解はないのだと思います。
コンセプトファーストで始まる商品もあれば、
魅力的な形やアイデアから始まって
コンセプトが後から見えてくる商品もある。
どちらも価値ある作り方で
大切なのは最終的にユーザーに愛される商品に
なるかどうかということなのだと思います。
今回のドリップペーパースタンドは
商品化には至りませんでしたが、
この経験を通じて私たちの
ものづくりに対する視野は確実に広がりました。
今後は感覚的な魅力とブランドコンセプトの
両方を大切にしながら、
固定観念にとらわれず、
もっと自由に歩んでいきたいと思います。