2025/04/24 08:47
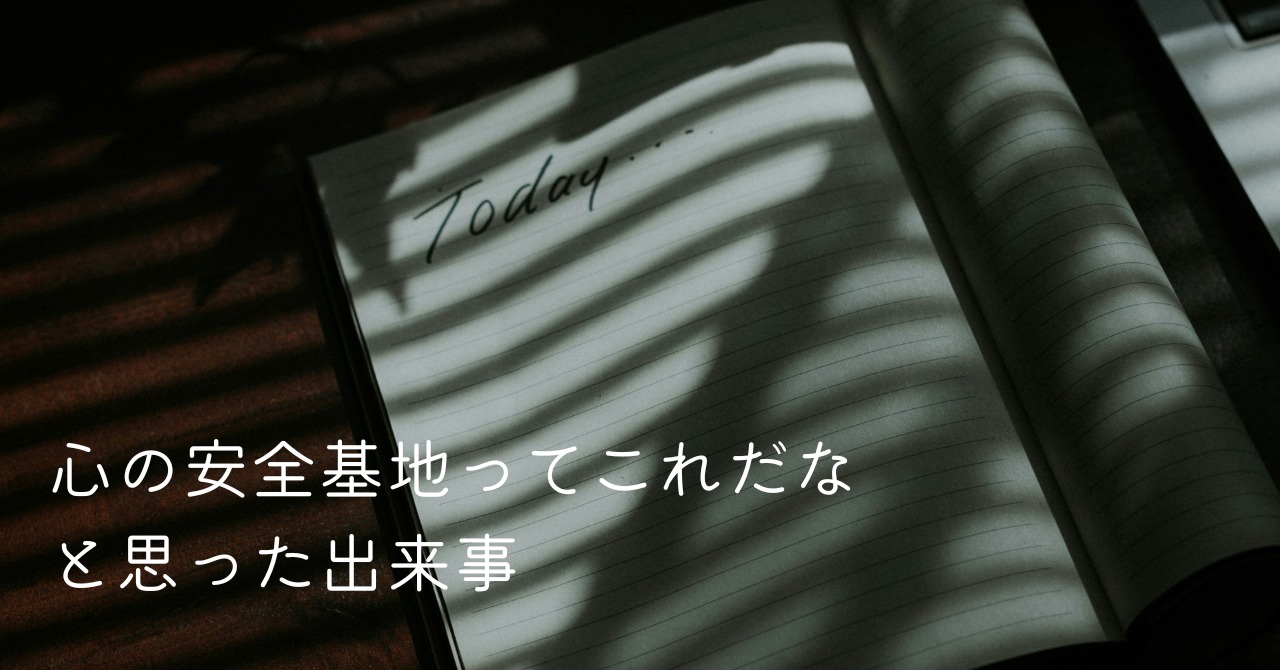
この春、お子さんが小学校に入学されたご家庭も
多いかもしれません。
新しい環境への期待と一緒に、慣れない集団生活や通学・・
親としては心配事が尽きない日々がつづきますね。
我が家も例外ではなく、小学1年生になった息子を見守る中で、
「心の安全基地」を改めて実感する出来事がありました。
-----
▶不安な時に立ち戻れる場所「心の安全基地」
冒頭からお話ししている「心の安全基地」という言葉。
心理学、特に愛着理論でよく使われる言葉ですが、
簡単に言うと、子どもが不安を感じたり、困難に直面したりした時に、
安心して立ち戻れる場所や存在のことです。
そこには、自分のありのままを受け入れてもらえる
という絶対的な安心感があります。
心の安全基地があるからこそ、
子どもは安心して外の世界へで出たり、
新しいことに挑戦したり、
自分らしさを表現したりすることができるようになるそうです。
それは、エネルギーを充電して
心を休ませるための大切な港のようなもの。
hattoが目指す「家族の絆をより濃く、より強く」
というコンセプトの根幹にも、
家族や家が、「心の安全基地」でありたい、
という強い願いがあります。
家族がお互いを認め、支え合うことで築かれる強い絆が、
子どもたちの、そして親自身の心の安全基地となるからです。
-----
▶慣れない下校、親の心配と息子の涙
我が家の息子はこの春小学校に入学したのですが、
学校まで少し距離があり、歩いて20分ほどかかります。
登校は、お隣の小学校の4年生のお姉さんと
一緒に行かせてもらっていますが、
下校は学童の集団下校。
集団下校といっても、同じ方面に帰る子が集まっているだけで、
途中で道が分かれたり、下校班の人数が日によって結構変わります。
多い時は7~8人いても、少ない時は新1年生が2人だけ、
という日もあって、特に下校については親としては心配が募ります。
そこで私は、息子が一人でも安心して帰れるように、
段階的に学校から離れて待つ「見守り作戦」を立てました。
下校初日は学校の門まで迎えに行き、集団の後ろからついて歩きました。
2日目も同じように見守り、3日目は少し慣れた様子だったので、
学校から2~300メートルほど離れた、道路を渡った先で待機。
4日目はさらに先の公園で待つ、という感じで
徐々に待つ場所を遠ざけていきました。
最終的には、家で待っていられるようになることを目指した作戦です。
そして迎えた5日目。これまでの最長距離になる、
家と学校のちょうど真ん中あたりで息子を待っていました。
しばらくして、学童のお兄さんお姉さんに付き添われた息子が
姿を現したのですが、大粒の涙を流しながら歩いていました。
付き添いの子たちも、なぜ泣いているのか分からない様子。
息子もひくひく泣いていて、うまく話すことができませんでした。
-----
▶言葉にならない「不安」と「頑張りたい気持ち」の葛藤
家に着いて、落ち着いてから息子に話を聞いてみました。
すると、「なんか、急に寂しくなってしまった」とのこと。
毎日新しい環境で頑張っているんだから、
そんな日もあるよね、と話しながら息子とも相談して、
次の日は前日よりも学校に近い、公園で待つことに決めました。
「そこまでなら、もし一人になっても帰ってこられるから大丈夫!」
「公園で待ってて」と息子には言われました。
でも、翌日その公園で待っていると、
息子はまた泣いて帰ってきました。
この日は学校の門を出た時からずっと泣いていたそうです。
再び落ち着いてから話を聞くと、
本人も「どうして泣いちゃうのか分からない」
「でも、なんか涙が出てくる」と言うのです。
学校自体は毎日楽しそうに行っています。
朝は「学校行きたい!」と言うし、
お友達との出来事や、学校でどんなことをしたのかも話してくれます。
幼稚園の頃に比べれば、
我慢したり、頑張ったりしなければならないことも増えたはずですが、
息子なりにそれを理解し、頑張ろうとしている姿も見られます。
嫌なことがあったというわけでもなさそうです。
では、一体なぜ涙が止まらなかったのか。
息子の中では「新しい環境で頑張りたい」という気持ちと、
「慣れないことへの不安」という気持ちが
揺れ動いている状態だったんじゃないかなと思います。
頑張りたい、でも不安、ちょっと怖い…
そんな揺れ動く心の中で、
張り詰めていた緊張の糸がぷつりと切れ、
感情が涙となって溢れ出してしまったのかな、という気がします。
言葉ではうまく表現できない、
複雑な心の状態を、体が正直に「涙」という形で表したのかな、と。
-----
▶一歩踏み込んだ「見守り」が心の安全基地を育む
息子の姿を見て、親としてどうすればいいのか、
改めて考えさせられました。
そして、やっぱり今は「見守る」しかない、という思っています。
「見守る」とは、
辞書では「注意しながら見る」「気をつけながら見続ける」
といった意味が書かれています。
でも、今回の経験を通して、
私はもう一歩踏み込んだ「見守り」をしたいと感じています。
息子の中でせめぎ合う「頑張りたい」と「不安」な気持ちを、
親である私が100%理解してあげることは、難しい。
それでも、その気持ちに「一緒に寄り添い、共に感じる」こと、
そして物理的にも心理的にも「そばにいる」こと。
これが、私が今すべき「見守り」だと考えています。
不安に押しつぶされそうになっている時、
どうしようもなく心細い時に、すぐ隣に誰かがいてくれる。
いつでも手を差し伸べてもらえる距離にいる。
そんな安心感こそが、子どもの心の安全基地を育む土台になる。
私たち親の存在、そして家という場所が、
息子にとっていつでも安心して帰ってこられる、
エネルギーを貯められる安全な港であること。
そう感じられた今回の出来事は、
親としての私にとっても大切な学びとなりました。
-----
▶家族の絆が心の安全基地を強くする
心の安全基地があることで、
子どもは安心して外の世界へ羽ばたいていけます。
たとえ失敗したり、傷ついたりしても、
「ここ(家、家族)に帰れば大丈夫」という安心感があれば、
また立ち上がって、挑戦する勇気を持つことができるのです。
この安心感こそが、自己肯定感を育て、
困難に立ち向かう力をつくってくれる。
小学1年生という、子どもにとって大きな変化の時期は、
親にとっても戸惑いや心配が多い時期です。
今回の息子のように、理由の分からない不安や
涙を見せることもあるかもしれません。
そんな時、すぐに答えを出そうとしたり、
無理に励まそうとしたりするのではなく、
ただそばにいて、その気持ちに寄り添うこと。
それが、心の安全基地を育む第一歩だと感じました。
新生活が始まったばかりのこの時期、
子育てには様々な悩みがあると思いますが、
一人で抱え込まず、周りを頼りながら、
そして何より子どもと一緒に成長していく気持ちで
向き合っていきたいですね。
この経験が、我が家の家族の絆を
さらに強くしてくれると感じています。
